こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
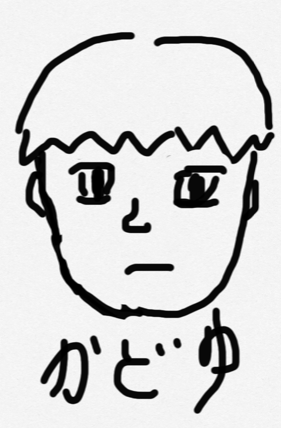
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は第40条労働時間の特例となります!
前回が法定労働時間、いわゆる原則だったので特例もありますということで…
労働時間の特例

条文をどうぞ!
といっても第40条については条文単体では内容が分からないので飛ばしても大丈夫です…
こんなものですよということで載せておきます。
第四十条
①別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
②前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
結局のところ何?ってことで解説していきます!
ポイント
一定の事業には原則の1週間の法定労働時間である40時間を超えて44時間まで労働させることができます。
その一定の事業というのは下記の通りです。
①商業
②映画・演劇業
③保健衛生事業
④接客娯楽事業
これら4つの事業で常時10人未満の労働者を使用するものが該当します。
一つずつ具体例を見ていくと、まず①商業というのは小売業や理美容業等です。
②映画・演劇業は読んでそのままですが、注意点としては映画の製作の事業は除きます。
「映画の製作を除く」と社労士試験では定番の論点ですが、具体的には何が除かれるのか一歩踏み込んで労基署に聞いてみました。
回答としては演者は特例が適用されて、カメラマン等のいわゆる裏方の事業には原則が適用されるとのことでした。
他に、映画館等の映写の事業については特例が適用、配給会社には原則が適用とのことでした。
といっても…例えば撮影現場という幅広い事業が参加するような場合は、
原則と特例が混ざってややこしいことになりかねないので、関係各所への確認することを怠らないようにしたいですね!
③保健衛生事業は病院や銭湯等の浴場業のことで、④接客娯楽事業は旅館、飲食店、遊園地等のことをいいます。
なぜこれらの事業に特例が認められているのかというと、
少数の方が働く上記のような事業場では人員の配置に頭を悩ませることが少なくないため、
労働時間をできるだけ延ばしているといったところです。
それでは今回は復習の条文は無しで、いきなりまとめます!
まとめ
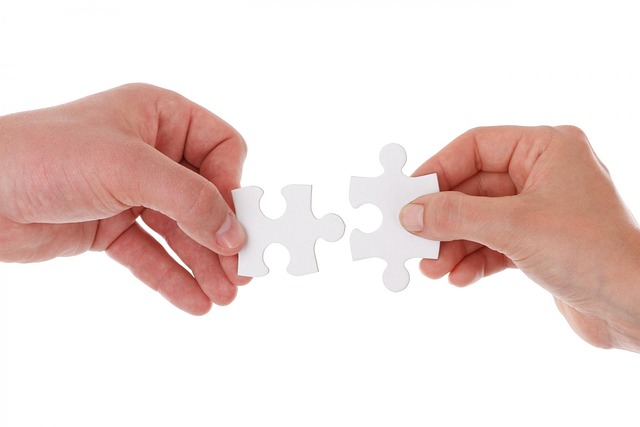
第40条労働時間の特例
- 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は1週間の法定労働時間が44時間となる
- 映画・演劇業のうち、映画の製作の事業については本条は適用されない
法定労働時間の原則については前回の記事でしっかり復習して、
今回の記事をお読みいただけますと幸いです!
今回もありがとうございました。
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりお願い申し上げます。
次回は第38条労働時間の通算について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!


