こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
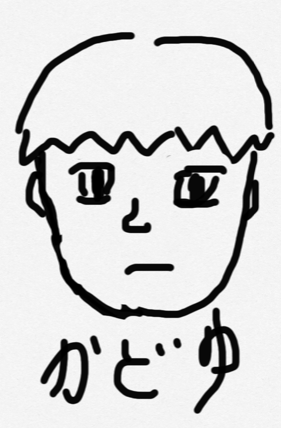
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は第19条解雇制限についてです。
実務の面でも関わることがあるかもしれないところなので、是非とも社労士試験を受験しない方にも見ていただきたいです!
解雇制限

条文はこちら。
第十九条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし書きがありますが、それについては後述します!
ポイント
まず本条の趣旨としては、上記のような休業中においては労働者を保護しましょうということです。
休業中ということは収入の保障がなく、生活が困難な状態かもしれないので解雇されないように制限があります。
「産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間」というのは、
労基法に定められているいわゆる「産前産後休業」のことです!
注意点としては、上記のような休業中でも、
契約期間満了で労働関係が当然に終了する場合は「解雇」ではないので本条違反となりません。
しかし、労働契約法や育児介護休業法等の規定との兼ね合いによっては解雇とみなされることもあるので、
引き続き更新されたと認められる事実がない限り慎重に…といったところです。
また、上記のような状態でも実際は休業していない期間や、
業務外で発生した負傷等(私傷病)による休業中はそもそも解雇制限の規定は適用されません。
罰則については下記の通りです。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
解雇が制限される期間について見てきましたがこの制限が解除される場合があります!
それが上記第19条の続きのただし書きにありますので見ていきましょう。
解雇制限の解除

第19条の続きです!
第十九条
~
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
こちらも見ていきます!
ポイント
まずは「打切補償」って何ぞやというところですが、これは条文にある通り労基法第81条に規定されているものです。
業務上の傷病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても治らない場合に、
使用者が、平均賃金の1,200日分の補償を行い、その後の期間については補償を行わなくていいというものです。
上記の「打切補償」を行えば解雇制限が解除されるということです。
打切補償は、労基法の療養補償を受けている労働者に対して行うものです。
ですが、最高裁判例では、労災保険法の療養補償給付を受けている労働者に対しても行うことができるとされており、この場合においても解雇制限が解除されます!
次に「事業の継続が不可能になった」といった場合ですが、
例えば地震や台風等により事業所が倒壊して営業ができなくなったというようなことです。
注意点としては、この場合には具体的には労基署長の認定を受ける必要があります。
ちなみに派遣労働者については、派遣元の事業において事業の継続が不可能かの判断が行われます。
この「認定」というのは…
解雇制限の解除ができる事実の有無を行政官庁が確認するといった意味合いで、
事実の有無の判断を使用者の独断で行うことを規制しているものです。
それでは、もし上記のような場合に認定を受けずに解雇してしまった場合はどうなるでしょうか?
これについては、「認定」というのは事実の確認に過ぎないので、
客観的にそのような事由がある場合には解雇制限は解除されることになり解雇は有効となります。
ですが…解雇は有効になりつつも本条の違反となることは覚えておきましょう!
こんなところで、ただし書きも含めて復習の条文です。
第十九条
①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
解雇制限の期間中においては労働者の責めに帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されないことにも注意です!
まとめ
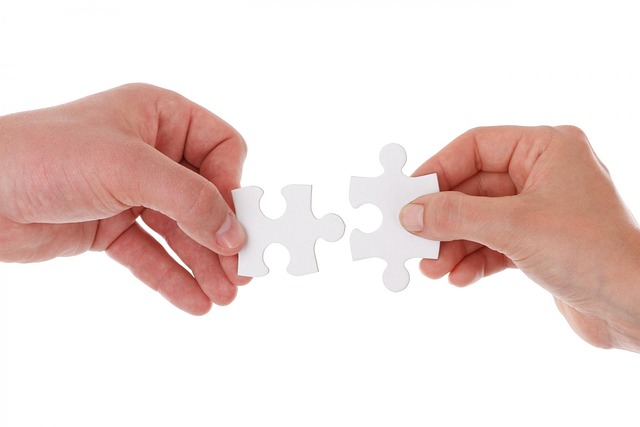
第19条解雇制限
- 業務上の負傷や疾病の休業期間、産前産後休業の後30日間は解雇が制限される
- 契約期間満了は解雇ではないので基本的には上記のような期間でも労働関係は終了する
- 実際に休業していない期間、私傷病による休業中には解雇制限は適用されない
- 打切補償を行った場合、天災事変等により事業の継続が不可能になった場合(要認定)は解雇制限が解除される
実務において解雇の分野はトラブルが発生しがちですし、
発生した場合には双方がしっかりと納得して解決することが求められるかと思います。
社労士試験を受験されない方にもこちらの記事がお役に立てれば幸いです!
今回もお疲れ様でした!
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。
次回は第20条解雇予告について解説します。
また次回もよろしくお願いします!


