こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
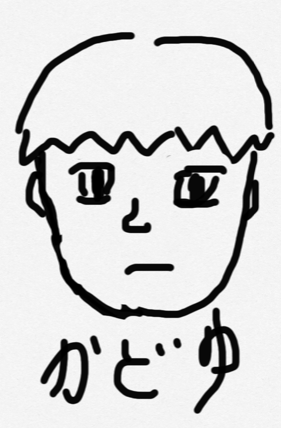
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回から労働契約の分野に入ります!
まずは労働基準法が持つ労働条件に対する効力について解説していきます。
前回がボリューム多めだったので今回は控え目に…
労働基準法の効力

条文を…
第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
サクッと解説します!
ポイント
労働基準法で定めてある労働条件は最低基準のもので、
それに達していないような労働契約は無効になります。
これは強制的に無効になるといったようなイメージで「強行的効力」といいます。
それでは無効になった部分はどうなるのかというと、
労働基準法で定められている労働条件が適用されることになります。
これについては「直律的効力」といいます。
労働基準法で定められている労働条件に直接律されるというイメージです。
例としてはこんな感じ…
労働条件:所定労働時間は10時間とする
↓
労働基準法にある法定労働時間は8時間なので無効に(強行的効力)
↓
労働条件にある所定労働時間は8時間になる(直律的効力)
ちなみに所定労働時間と法定労働時間の違いは…
所定→事業所で定められた労働時間
法定→労基法で定められた労働時間
第1条にも「最低の~」というという文言がありまして、
以前に解説した記事もあるので宜しければご参照ください。
もう復習の条文です!
第十三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
一文目は「強行的効力」、二文目は「直律的効力」のことですね!
まとめ
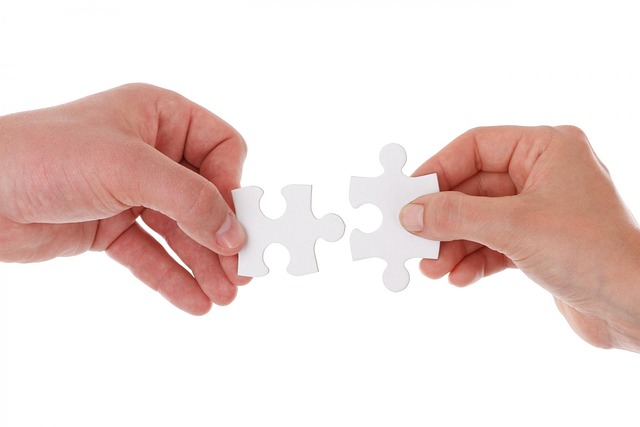
第13条労働基準法の効力
- 労基法で定めている基準に満たない部分の労働条件は無効になる(強行的効力)
- 無効になった部分は労基法で定めているものになる(直律的効力)
労働契約全体が無効になるわけではなく、
基準に達しない労働条件が部分的に引き上げられることに注意です!
今回は手短に終わります!
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。
今回もお疲れ様でした。
次回は第15条労働条件の明示について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!



