こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
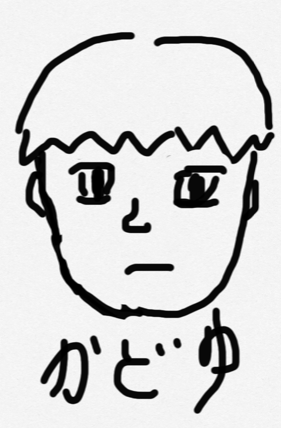
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は第27条出来高払い制の保障給にサクッと触れて、第12条平均賃金についてしっかり解説していきたいと思います!
それではよろしくお願いします!
出来高払制の保障給

条文です!
第二十七条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
もちろん成果も大事ですが…
それでは解説してまいります!
ポイント
営業ノルマが達成できていなかったり、成果物の一部に不具合があったとしても、
労働させたのならその時間に対して一定額を支払うといったものです。
また、例えば材料不足によって上手くものが作られず出来高が少ないといったような時に、
賃金を不当に下げることを防止するということでもあります。
この一定額というのは、少なくとも平均賃金の100分の60を目安としております。
これは労働者の生活を保障するための休業手当と共通していますね!
休業手当についても解説しておりますので、そちらもお読みいただけますと幸いです。
念のため…保障額については最低賃金を下回ってはいけません。
生活保障という趣旨が重要ということが分かります!
当然の話にはなりますが、
労働時間に対しての保障給ですので、欠勤や遅刻、早退等で就労しなかった時間については支払う必要はありません。
罰則は下記の通りです。
30万円以下の罰金
復習の条文です!
第二十七条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
保障額について、少なくとも平均賃金の100分の60を目安と上述しました。
その「平均賃金」について解説していきます!
平均賃金

条文ですが、但し書き等もあり全て載せると凄く長いのでまずはこちら…
第十二条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
記載以外の部分も分けて解説しますのでご安心を!
ポイント
まず「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間」とあります。
「算定すべき事由」と「事由の発生した日」というのは、下記の通りです。
(後述しますが、算定事由発生日というのは、
賃金締切日がある場合は「直前の賃金締切日」となりますので下記は参考程度に…)
<算定すべき事由> <算定事由発生日>
・休業手当 → 休業日
(2日以上の場合は最初の日)
・解雇予告手当 → 解雇通告日
・有給休暇 → 有給休暇を与えた日
(2日以上の場合は最初の日)
・災害補償 → 事故発生日または
診断によって疾病に
より疾病の発生が確定した日
・減給の制裁 → 制裁の意思表示が
相手方に達した日
休業手当は前回に出てきましたね!
他に見覚えのない事由もあるかと思いますが、全て別の記事で解説します!
なお「算定すべき事由の発生した日以前~」とあり、事由発生日も含むと読めますが、
実際には事由の発生日は含めずその前日からの3か月間で計算していきます。
なぜそのような取り扱いなのかというと…
例えば災害補償のケースで事由発生日を含めると、ケガをした日はきっと早退して減給されており、
その日を計算に入れると少しでも労働者の不利益に繋がってしまうからと考えましょう!
と、散々、算定事由発生日について書きましたが、
上述した通り、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算するものとしております。
式で書くとこんな感じ↓

ちなみに賃金締切日当日に算定事由が発生した場合は、その前の締切日から3か月となります!
もし雇入れて3か月に満たない場合はその期間で算定します。
(この期間中に賃金締切日があるなら原則としてその賃金締切日から起算することになります。)
賃金総額に含めないもの
上述した条文中や式に「賃金総額」とありますが、そちらにそもそも算入しないものについても定めがあります。
第十二条
~
賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
これらを全て含めたら算定のタイミングによってバラつきがあったり、平均賃金が凄い額になったりしますね…
「臨時に支払われた賃金」というのは例えば、下記のようなものです。
・創立〇〇周年を記念して手当が支給されるといった臨時的、突発的に支払われたもの
・結婚祝金や見舞金など、就業規則等に明確な支給条件が定められているが、発生が不確定で非常に稀なもの
「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」というのは分かりやすい例でいうと賞与です。
年に3回以内の頻度で支給されているような賞与は賃金総額に算入しないということです。
賞与という名称に囚われないように注意しておきましょう!
例えば賞与だからといって2か月に1回支給されるようなものは賃金総額に含みます!
また、あらかじめ支給額が確定しているものも賞与といえません。
例えば年俸制の方で、毎月支払う分と賞与が合計された額として年俸額が確定している場合は、
既に支給額が決まっていることになるので賞与の部分も賃金総額に含める必要があります。
それでは6か月に1回支給される定期券代はどうなるでしょうか?
これは毎月の通勤費を単にまとめて支払っているといったものですので賃金の総額に含まれます。
そして「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は、
法令や労働協約で定めていない現物給与のことで賃金とはいえないので当然のように除外されます。
賃金の定義についても記事がありますので復習にどうぞ!
算定期間から除く期間と賃金
それでは、平均賃金の算定する3か月の中に、例えば産前産後休業の期間がある場合はどのような扱いになるでしょうか?
その期間中の日数と賃金は算定期間から除かれることになります。
これについても第12条で定められています。
第十二条
~
前二項期間(平均賃金の算定期間)中に、次の各号(下記)のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間(平均賃金の算定期間)及び賃金の総額から控除する。
(一部に加筆等しております)
算定期間から除かれる日数と賃金は下記の通りです。
- 業務上の負傷や疾病による療養のために休業した期間
- 産前産後の女性が労基法65条により休業した期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業をした期間
- 試用期間
どれも期間中は賃金が下がったり低くなったりしてしまう期間かと思います。
いくつか注意点として、①は私傷病については対象外となります。
④は似ているものとして看護「休暇」、介護「休暇」というのものがありますが、
これらについては算定期間から日数と賃金総額は除かれません。
考え方としては…
育児「休業」、介護「休業」は雇用保険法で給付金が定められているのに対して、
上記「休暇」については給付金等の定めはなく有給か無給かは事業主に委ねられています。
なので、法律で一様には定めることができないということで…
⑤の期間中ですが、もし何らかの算定事由が発生した場合は、
その試用期間中の日数と賃金で平均賃金を算定することになっています。
日数と賃金が除かれる期間というのは、
労働者の責任ではなかったり法律で保護されている部分で労働者の不利益にならないようにするためといったところです!
それでは、復習がてら改めて平均賃金を算定する式を見てみましょう!

…お気づきだろうか……
日給者や時給、出来高払いの人で労働日数が少ない場合、暦日数で除したら平均賃金がとても低くなってしまうかもしれないことを…
日給者や時給者等の場合
このように定められております!
第十二条
~次の金額を下つてはならない。
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
(一部に加筆等しております)
式です!

簡単にですが例で比較してみましょう!
日給:6,000円
1月(暦日数:31日) 労働日数:10日 賃金:60,000円
2月(暦日数:28日) 労働日数:5日 賃金:30,000円
3月(暦日数:31日) 労働日数:10日 賃金:60,000円
原則の式:賃金総額150,000円÷総暦日数90日=平均賃金は約1,667円
最低保障額の式:賃金総額150,000円÷労働日数25日×60%=平均賃金は3,600円
→最低保障額が適用
それでは、例えば基本給は日給制だけど手当が月給制の場合はどうなるでしょうか…
日給等と月給等が組み合わさった場合
こちらも条文で定められております。
第十二条
~次の金額を下つてはならない。
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
ややこしくなってきましたよね…
式はこちら…

月給等の部分と日給等の部分は分けて計算しましょうということですね!
この場合、月給等の部分には最低保障が適用されず、日給等の部分にだけ適用となるので注意です!
すみません、またまた長くなりましたね…まとめの前に復習で平均賃金の根幹の部分です!
第十二条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
まとめましょう!
まとめ
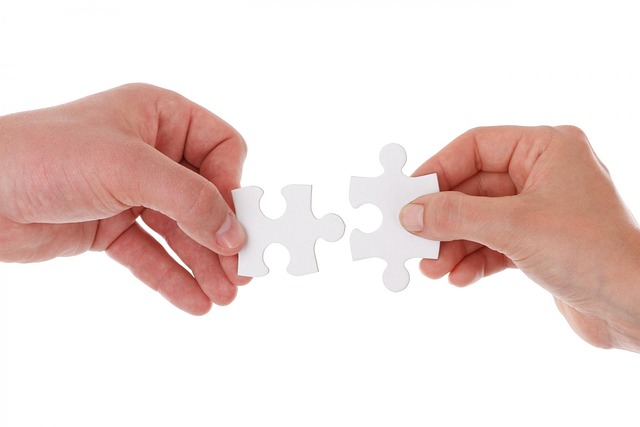
第27条出来高払い制の保障給
- 出来高が少なくても労働時間に応じた一定額を保障する
- 平均賃金の60%を目安として保障することが妥当であるとされている
第12条平均賃金
- 平均賃金の原則額を算出する式を覚えておく
- 臨時に支払われた賃金等は賃金総額にそもそも算入しない
- 育休中、試用期間中等の日数と賃金は算定期間から除く
- 日給者等、平均賃金を原則の式で計算した場合に不当に低くなる場合は最低保障額が適用される(月給等が絡んだ場合の式も確認しておく)
きっと長いお時間お付き合いいただきありがとうございました…
今回も社労士試験だけでなく実務において役立つ部分かなと思っておりますので、
お休みの日などお時間ある時にじっくりとお読みいただければと存じます。
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです!
大変お疲れ様でした。
次回は労働契約の部分に入りまして、
ガイダンスのような部分になりますが第13条労働基準法の効力について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!




