こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
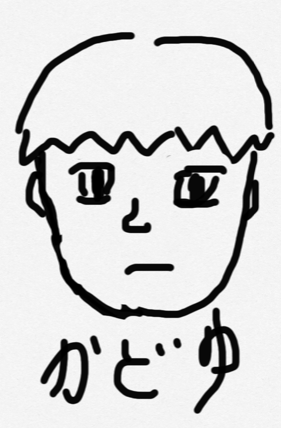
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は労働基準法の第1回目となりますので、
そもそも労働基準法とは?ということにもざっくり触れた後に、労働条件の原則・決定について解説していきます!
労働基準法とは?

略して労基法と呼んだりもします。
社会人の方はもちろん、学生の方も何となく聞きなじみがある法律かと思います。
昭和22年に労働者を保護することを目的として定められました。
労働条件の最低基準を定めているものになります。
早速、第1条労働条件の原則から見ていきましょう!
労働条件の原則

第1条は条文が重要なので載せておきます!
第一条
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
ポイント
比較的読みやすいかと思いますが、どこかちょっとお堅い感じがしますよね。
まず①の部分ですが、こちらは憲法25条1項の生存権に関連したものとなります。
「労働条件ちゃんとしてね」といったような宣言的規定といったところでしょうか。
(頑張ってたくさん働いているのにまともに生活できなかったら辛いですよね…)
そして、②は特に重要です。
労基法で定められている労働条件は文字通り最低基準のものです。
なので、労働関係の当事者(社長と従業員というイメージでOKです)で、
労基法の基準を悪用しないで、むしろそんな基準を上回るよう頑張っていこうねということです。
例えば、とある会社Xでこんなことがあったとします↓
社長「総務のAさん、うちの1日の労働時間ってどんな感じでしたっけ?」
Aさん「就業規則を見ると、始業9:00、終業17:00で休憩が1時間なので労働時間としては7時間です」
社長「おお、そうでしたね。労基法に定められている1日の労働時間の上限は何時間だっけ?」
Aさん「あ、えーっとですね、8時間となっております」
社長「そうなの!?じゃあ労基法にそう書いてあるから8時間に変更しちゃうね」
(これは…)
これこそが、
「労基法の基準を理由として労働条件を低下させる」
ということになり第1条違反になります。(たとえ社長と従業員の合意があったとしても)
X社の就業規則で定めた労働時間7時間から、労基法の労働時間の上限である8時間にするというのは労働条件を低下させたということになります。
「いやいや、働きたいから労働時間は長い方が嬉しいんですけど??」
といったご意見もあるかもしれませんが一旦飲み込んでいただいて…
それでも納得いかんぞという方にもう一例…
労基法ではいわゆる残業代の割増率も定めておりますが、
とある会社の就業規則で労基法を上回る割増率を定めておりそれが適用された場合に、
「お金要らないから増額やめて」という方はきっといないですよね…
このように労働基準法第1条は、
労基法を理由に労働条件を低下させないことは当たり前のことで、
もっと良い労働条件にしていこうねという意味合いもあるのです。
それでは復習として上記を踏まえて、改めて第一条の条文です。
第一条
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
因みに、労基法を主たる理由として労働条件を低下させることは上記の通り違反となりますが、
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、本条には抵触しないということも覚えておきましょう!
次は第2条です!
労働条件の決定

こちらもまず条文から。
第二条
①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
ポイント
語句はともあれ第1条よりは分かりやすいと思います。
まず①は、
どうしても労働者(従業員)より使用者(社長)の方が立場が上というイメージになりがちな中で、
労働条件を対等に決めるべきですよといったことを定めております。
そして②は、そのままになりますがお互い決めたことを守りましょうねということです。
労働協約、就業規則、労働契約というのもここで説明しておきます。
名前は違えど労働者と使用者との約束事のことで優先順位等が違います。
それぞれの語句説明はこちら↓
労働協約:労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件等に関する協定
就業規則:労働者が就業上守るべき規律及び労働条件等について使用者が定めた規則
労働契約:個々の労働者が使用者が結んだ一定の労働条件の下で労働力を提供することを約する契約
続いて優先順位ですが、下記の通りです。
法令(労働基準法)>労働協約>就業規則>労働契約
これは上記、第1条の労働条件の原則で書いた内容と関連します。
労基法に「達しない」労働協約、就業規則、労働契約に定められている労働条件の一部は無効になり、
その部分については労基法で定められているものが適用されます。
労働契約そのものが無効になるわけではなく、基準に満たない部分だけ労基法によるものとなります。
そして労働協約がちょっと特殊でして、
労働協約に「違反する」(違っている)就業規則、労働契約にある労働条件の部分が無効になります。
これは例えば、就業規則や労働契約である部分について、
労働協約より有利な条件が定められていても、
労働協約と違っていればその部分は無効になってしまうということです。
労基法に「達しない~」と労働協約と「違っている~」の部分は注意しておきましょう!
第2条はこのような具合で条文の復習いきます!
第二条
①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
語句説明でちょっと逸れてしまいましたが、それぞれ意味を覚えておいた方がいいのでお願いします!
まとめ

第1条労働条件の原則、第2条労働条件の決定
- 労働基準法を理由として労働条件を低下させてはならない(労使の合意があっても×)
- 他に決定的な理由(社会経済情勢の変動等)があれば第一条の②に抵触しない
- 法令(労働基準法)>労働協約>就業規則>労働契約の力関係を覚えておく
- 労働基準法に「達しない」、労働協約と「違っている」の部分に注意
今回は労働基準法の1回目で第1条、第2条について解説しました。
条文を解きほぐしたような内容になりましたが、
その内容についてより深い理解に繋がりましたら幸いです。
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。
次回は労働基準法第3条の均等待遇の原則について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!


