この記事では、
- 社労士ってたまに聞くけど何?
- 試験は誰でも受けられる?
- 何となく興味はあるけどよく分からない
といったようなお悩みを解決していきます。ざっくりとでもご理解いただければ幸いです!
<こんな人が書いています>
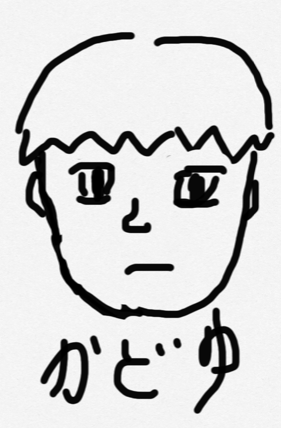
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・社労士事務所にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は開業してお仕事募集中です!

「社労士」の正式名称は「社会保険労務士」といいます。
詳しくは、全国社会保険労務士会連合会HPにも載っています。
↓↓↓
結局のところは何ぞやとなった方、
とてもざっくり言うと、
働くことや年金に関する専門家です。
とりあえず社労士はこんなイメージで問題ないかと思います!
何をしている人?

どんな人か分かったところで、どういう仕事をしているのか見ていきましょう!
働く人たちの色々な手続き
働く人たちの悩みを聞いて解決する
またまたざっくりとですがこんな感じです。
すこーしだけ嚙み砕いてイメージしやすくします!
働く人たちの色々な手続き
文字通り様々な種類がありますが…
代表的で重要なものとして、働く人が会社に入る時の手続きがあります。
馴染み深いものですと、入社後に保険証を受け取るかと思います。
(扶養に入っている場合など保険証が発行されない方もおります)
会社にもよるのですが、
その保険証を発行するための手続きを社労士がやっていたりします。
他にも日々の生活していく中で起きるかもしれない“もしも”の時に、
生活の助けとしてお金が貰えたりと社労士が行う重要な手続きがたくさんあります!
働く人たちの悩みを聞いて解決する
日々働いていく中で色んな悩みや、トラブルが発生することがあると思います。
上司や同僚と合わない、セクハラ・パワハラに悩んでいる…といった社員さんから寄せられた悩みや、
社長さんの方でも、会社のルールを見直したい、問題を起こす社員に対する対応…など。
労使双方に十人十色の悩みがあって、それらを解決に導いていきます。
ということで改めて社労士は…
働く人たちの様々な手続きをしたり、悩みを解決したり、私たちの社会にとって大事なお仕事をしているということです!
どうすれば社労士になれるのか

国家試験に合格して、社会保険労務士連合会に登録する必要があります。
試験について
年に1回、例年8月の第4日曜日に実施されております。
受験生時代の僕にとっては夏の風物詩でした…
どんな人が受験できるの?
社労士連合会のホームページに詳しく載っておりますが、
まず多くの方に当てはまりそうな条件をざっくり書くと、
大学、短大、専門学校等の卒業生の方は受験資格を満たしているかと思います!
※大学在学中の方でも単位数によっては受験できます。
上記以外では、実務経験や他の資格試験に合格されている方も受験できます。
改めて見てみると、色んなバリエーションがあるんだなあと思いました。
受験してみたい!と思っている方は、
受験資格を詳しく上記のホームページでしっかりとチェックしておきましょう!
試験科目
さて、当日立ち向かうべき相手ともいえる試験科目ですが下記の通りとなっております。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
以上、10科目です。
うわ多いなあって思った方、同感です。今も変わらず思っております…
これをご覧になって戦意喪失されている方…
大丈夫です。きっと成し遂げられます。
昔から物分かりが悪いと自負している僕ですが、
社労士試験に合格できた勉強の進め方を以下の記事で公開しているので、
是非お読みいただいて皆さんの不安を払拭できたら幸いです!
いずれ各科目の勉強のポイントについて記事にしたいと思っていますので、
無理かも…となっている方の気持ちのハードルを少しでも下げていきたいです。
あと、重要なことを書き忘れていました。試験は全てマーク式です。
記述して回答する問題はありません。これだけで少し気が楽になりませんか?
かなり極端な話ですが、合格するだけなら鉛筆を転がして…といったことも可能です。
試験当日の流れ
9:30 開場
10:00 着席
10:30 試験開始(選択式)
11:50 お昼休憩
13:20 試験開始(択一式)
16:50 終了
上記のようなスケジュールとなっております。
出題形式についても解説しておきます。
午前は選択式といって、問題文の空欄に入るべき正しい単語を語群から選んでいく穴埋め問題です。
午後の択一式は、選択肢1~5の中でどれが正しいか選んでいくといったようなものが大半です。
(たまに選択肢1~5で間違っているものはいくつあるかといった、一ひねりされたものもあります…)
朝から夕方までの長丁場なので集中力を維持するのがなかなか大変かもしれません。
4度目の挑戦の時にビッグサイトで受験したのですが、終了後に海沿いでバーベキューをして夕陽を見ながら飲んだビールが疲れた体に沁みわたりました…
合格率や合格基準点について
合格率は大体近年の傾向を見ていると、
4~6%の範囲で動きがある感じとなっております。
世の中に色々な資格試験がある中で、
それなりに低いといえるかもしれません。
次に合格基準点ですが令和5年度ですと、
選択式試験総得点40点中26点以上、かつ各科目5点中3点以上
択一式試験総得点70点中45点以上、かつ各科目10点中4点以上
となっているのですが、受験された方の正答率等でその年ごとに変わることがあります。
そして合計点がいくら高くても、
上記にある通りどれかの科目が基準の点数に達していないと不合格となってしまいます。
これがいわゆる「足切り」というやつです…
この足切りこそが社労士試験の合格率の低さの要因の一つでもあると言われています。
そして一定の点数を取れている科目があっても結果は持ち越せず、
また次の年は改めて全科目を受けなければなりません。
合格発表など
合格発表は大体10月1週目に発表があり、
2023年に関しては10月4日(水)でした。
その日の官報に掲載されます。(インターネットでも見ることができます。)
合格していると、色々な手続き書類が入っている分厚めの封筒が書留で来ます。
不合格の場合はハガキがポストにポツンと入っているだけです…
厚生労働省に合格者の受験番号が載っている資料があるという情報をどこかで聞いて、
直接わざわざ見に行ったことを思い出しました。
登録について
さあ晴れて合格だ!たった今から俺は社労士だぞ!!というわけにはなりません。
連合会の社労士名簿に登録をして、はじめて社労士と名乗るができます。
ですが、その登録にも条件があり、
・実務経験2年以上
・事務指定講習の修了
このどちらかを満たしていなければなりません。
ちなみに僕は事務指定講習を受けました。
今思えば、前職の事務所に3年勤めさせていただいたので、
後述にある受講料が節約できたなあとちょっと後悔してます…
事務指定講習について
面接指導課程と通信指導課程の2つのうちから選択し、
eラーニング講習(どちらの課程でも必須)の組み合わせで行います。
(2024年9月19日時点で社労士連合会の資料を見ると、
面接指導課程についての記載がなかったのでそちらは現在行われていないかもしれません)
まず面接指導課程は、いわゆる講義のようなものです。
4日間会場で受講するか、課題をこなして添削してもらう2パターンがあります。
僕は本当は会場での受講がしたかったのですが、
申し込みの締め切りが過ぎてしまっており通信指導課程で受講しました。
会場での受講について、周りは歳は違えど同期のような方たちばかりなので、
その場で名刺の交換等ができ次に繋がるお付き合いの場にもなったりするそうです。
次に通信指導課程ですが、4か月の間に様々な手続き書類を作成して、
それを郵送して添削をしてもらうといったよくある通信講座のようなものです。
現在はe-Govを利用したオンラインによる手続きが多いですが、
手書きで申請書類を作成していく体験のようなものができるのは良いなと感じました。
eラーニングは映像を見て簡単なテストに回答するといったものになります。
事務指定講習の費用ですが、77,000円となっております。
決して安くはないと思うので、
急ぎでの登録が必要ないという方は実務経験2年の条件を満たして登録の方がいいかもしれません…
登録の種別について
種類としては、
- 開業社会保険労務士
- 社会保険労務士法人の社員
- 勤務登録
- その他登録
4つあります。
簡単に、1.は文字通り開業する方ですね。
2.は社労士法人に属していて社労士資格を持った役員のような方です。
3.は社労士として従業員として会社等で働いている方にあたります。
4.はちょっと難しいのですが、ある組織にいても社労士としての仕事はしておらず、
かつ、3.のように勤務登録をしていない方があたるかと思います。
自分が合格後にどの種別で登録すればいいか迷うことがあるかもしれませんので、
こちら等参考にして登録に進みましょう!
※登録には登録料、年会費等、
都道府県によって多少のバラつきがありますが、何だかんだで色々と費用がかかります。
さいごに

登録できたら晴れて社労士です!!
決して高いとは言えない合格率の試験を突破して、実務経験2年だったり事務指定講習だったり、
時間やら何やらかかる道のりを進み続けたからこそ喜びもひとしおです!
科目数や合格率等、様々な厳しい側面もお伝えしましたが、
それを踏まえた上で社労士に少しでも興味がある方の背中を押せていたら幸いです。
僕もまだまだかけだしではありますが、
同じ空の下、皆様と一緒に頑張っていきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
(何かご質問等ありましたらお問い合わせまでいただけますと幸いです!)


