
いきなりこいつは何を当たり前のこと言ってるんだと感じておりますよね!
この記事を読んだ後に、これから初めて社労士試験に挑戦する方や、
自分にできるかな…と思っている方の背中を後押しできていれば幸いです。
また、現在勉強中であったり、
何度か挑戦して自信をなくしてしまっている方のモチベーション復活に繋がればいいなとも思っております。
<こんな人が書いています>
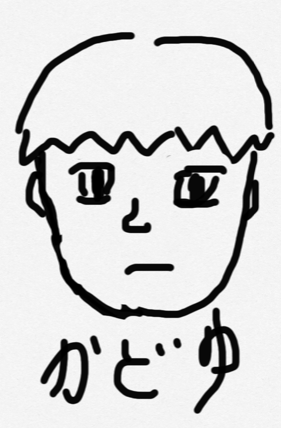
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
筆者は頭があまりよろしくない

はじめに…
僕は頭が良くありません。
自分で言ってて悲しくなりますが、
学生の頃から社会人の現在に至るまでそれを痛感する場面が多々ありました。
通知表での評価も芳しくなく、
大学受験は現役時に全て不合格で浪人するなどずっと勉強は苦手でした。
それでも社労士試験は合格することができます。
極論ですが、暗記さえできれば突破できます。
そして暗記は根気さえあればどうにかなります。
暗記が苦手なら理解を心がけると記憶に残りやすいです。
色々と残念な僕でも合格できたので、自信がないなあという方は参考にしてみてください!
心がけること

社労士試験は何といっても科目数が多いです。
それに伴い、合格に必要な勉強時間は1,000時間以上と言われています。
なので途中で挫折してしまう方が多かったりします。
分厚いテキストや、積み上げられた問題集を見て、
「これを全部やるのか…」と、改めて目の前の現実にげんなりしてしまいますよね…
挫折してしまう方が多いからこそ、とにかく大事なのは、
何が何でも全科目をやり通すこと!走り抜けること!
これが大事です!最初はあまり理解できていなくたって大丈夫です。
もうなりふり構わず1週でもいいので全科目通す!
これで合格の可能性が格段に上がります!
いきなり100%理解できなくても折れない気持ちです!
勉強法など
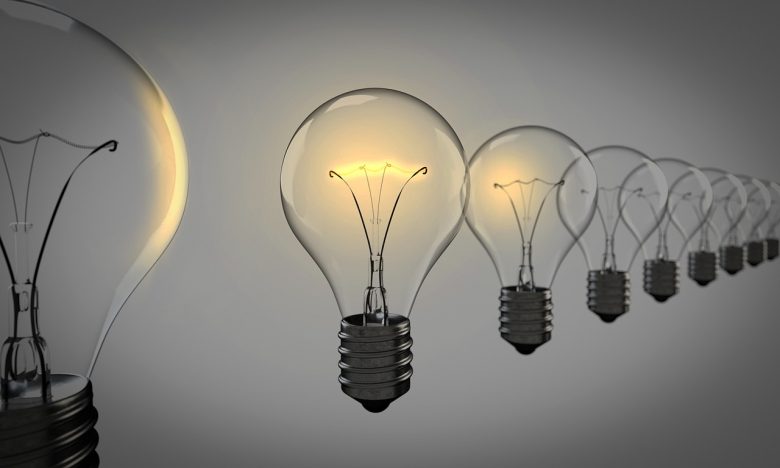
さあ勉強するぞという気持ちが高まってきたでしょうか。
ここからは、講義やテキストの見方など自分が実践していたことを書いていきます!
講義を受ける機会がない完全独学で挑む方についても、
テキストや過去問の取り組み方を書いていますので役立つかと思います!
メモは青ペンで
テキスト等に書き込みをする時があるかと思いますが、そんな時は青ペンをおすすめします。
青色には集中力を高めてくれる効果があるといわれており、
試験範囲が広く、覚えることが膨大な社労士試験においては、
普段の勉強でしっかり集中してインプットしていくということが重要です。
好きな色を使ってモチベーションを保つことも大切なのですが、
もし特にこだわりがないという方は青ペンを使ってみてはいかがでしょうか。
「何色を使ってもそんな大差ないでしょう」と思った方!確かにそう思う気持ちも分かりますが、
本気で合格したいからこそ、合格に近づけそうなことはどんなことも取り入れていきましょう!
講義について

対面であったり動画だったりで受講スタイルは様々かと思いますが、
僕は動画だったので、こちらではどのように視聴していたか書いていきます。
ちなみに理解力に自信がない方は動画での受講をおすすめします!
冒頭にも書いた通り、僕がそんな人だったので、
何度でも見返せる動画での受講スタイルを選びました。
あとは時間ができた時にいつでも見られるのもいいですよね。
対面の講義でしか味わえない独特の緊張感も好きです!
視聴時に心がけていたこと
1回目はそれなりの力具合で見ていました。
1回目でいきなり覚えられればいいですが、
初めて触れることだらけでそんなことは難しかったです…
よく分からなかった部分はまた見ればいいや~ってぐらいに思っておりました。
完璧に落とし込まなきゃ…と気合いを入れすぎた結果疲れてしまい、
全科目やり切る前に続かなくなってしまうこともありますからね…
とりあえずの気持ちで、全体を通して視聴してみましょう。
そして2回、3回と視聴したりテキストで振り返ったりしていくうちに、
全く頭に入ってこなかった部分が浸透してくる感覚が来るはずです。
なので1回だけ見て、「分からない、自分には無理だ」と諦めるのはもったいないですよ!
テキストについて

テキストは講義前に予習しておくのが望ましいかと思います。
受講前に、自分の中ですんなりと頭に入ってこない部分などを事前に把握しておくことで、
講義中に特にここをしっかり聞いておこうという意識ができるようになるかと思います。
特に対面での講義等、見逃しや聞き逃しができないような時は、
置いてけぼりにならないように予習をして頭に入りやすいようにしておきたいですね!
上記で偉そうに書いておきながら僕は動画だったのでテキストで予習はせず、
視聴しながら都度ストップ等で納得するまで繰り返しておりました…
後述しますが、
テキストには自分なりに噛み砕いた文言や気付いたことをたくさん書きましょう!
講義とテキストで相互補完
ここまで講義とテキストで、ある科目を一通り学習ができたかと思います。
この時点で完全に落とし込みができていなくても問題ありませんよ!
むしろ僕個人の感覚としては、やっとスタート地点に立てたといったところでしょうか…
ここから講義時のメモやテキストの熟読でしっかりと頭に入れていきます。
ここが根気を発揮する場面かと思います。
過去問でアウトプットに取り組む前段階ですので、
過去問の学習効果を高めるためにしっかりと論点等を把握しておきたいところです…!
講義やテキストを見ても…
ちょっと寄り道ですが講義やテキストを見返しても、
どうしても自分の中に落とし込めてないなあと思う部分がありませんか?
(僕はそんなことがそこそこありました…)
そんな時は、インターネット等で調べてみるのもいいかと思います。
テキストとはまた違った観点からの解説を読むことで、
意外にもスッと腑に落ちたりすることがあります。
条文ができた背景や、その日数や年数など覚えるべき数字の根拠が分かると、
知識の補強になって、急に点と点が繋がり理解できることもあります。
暗記は「覚えたい事」に何かを関連付けることで、より記憶に残りやすくなります。
(昔流行った商品を思い出した時にCMソングや映像が一緒に頭に浮かんできたりしますよね!)
もちろん人によっては勉強時間が限られている場合もありますので、
手っ取り早く暗記ができれば問題ありませんが、
覚えたはずなのにまた忘れてる…といったことが繰り返されてしまう時は試してみてください。
急がば回れといったやつです!
過去問について

いよいよ実践です!
択一式と選択式の過去問があるかと思いますが個人的な力の入れ具合としては、
択一式8.5:選択式1.5ぐらいの感じでいいと思います。
理由としては、択一式の過去問を解くことで選択式の対策ができてしまうので、
択一式を取り組むことに力を入れていきましょう!
過去問に慣れるまで
1週目は肩に力を入れすぎない程度に解いてみましょう!
まず過去問に触れて慣れていくことが大事です!
その中で、あれ?ここ全然理解できていないかも…となったら、
テキストに戻ってその過去問の論点部分を読み込みましょう。
テキストを読むだけでは気付かなかった苦手な部分の洗い出しができます。
2週目ぐらいから間違えた問題に印をつけたり、
テキストの該当部分に問われた論点の加筆をしてもいいかもしれません。
過去問にチェックボックスのようなものがあるかと思いますが、
僕は正答できた問題にはチェックや〇を付けず、×や△など苦戦した記録が分かるようにしてました。ボックス数も限られていたので…
そうすることで自分の苦手部分が補強された質の高いオリジナルテキストが出来上がっていきます!
過去問に慣れてきたら
繰り返し過去問をやっていく中で、
〇×や正解の選択肢を覚えてしまい学習効果が不安になってしまうことがあるかと思います。
そんな時は正解の根拠を頭の中で説明しながら回答するのがおすすめです!
何度か過去問をやってテキストも見返していくうちに論点等が頭に入っているかと思います。
この選択肢は「~だから〇」、「~じゃないから×」といったように、
自分の中で選択肢を精査していくことで論点を覚えて落とし込めているか確認ができます。
そのように繰り返しやっていくうちに、
頭の中から論点を引き出すのが早くなり、回答スピードも上がっていきます!
とにかく過去問はガンガンやりましょうー
選択式はいつやる?
択一式の過去問を頑張った方がいいのは分かったけど、
選択式はどのタイミングでやるのよってところですが直前期で問題ないかと思います。
択一式を頑張ってきたおかげで、
選択式の文章を見た時に抜けている単語が自然に頭に浮かぶようになっているのが理想です!
選択式の問題を解く際には、
選択肢を見てから回答するのではなく、これかな?という単語を頭に思い浮かべてから選択肢を見る
これを意識して進めると効果があるかと思います!
さいごに

講義、テキスト、過去問の取り組み方について僕の経験を基に書かせていただきました。
最初にも書きましたが、
極論、社労士試験は暗記できれば合格できます。
そして、暗記は根気さえあればどうにかなります。
ですが社労士試験は暗記するべきポイントが多いからこそ、
繰り返し勉強して理解していくことがとても重要です。
そして、論点が頭に刷り込まれ得点できるようになっていきます。
記事タイトルに理解は近道と書きましたが、
勉強をしていくうちに自然とポイントを覚えて問題が解けるようになっていると実感したからです。
(僕は理解力がなかったからこそ過去問を全科目7周ほどやりました…)
理解と暗記のサイクルは勉強の基本かと思いますが、
難関資格である社労士試験はその基本ができれば合格できるはずです…!
学校やお仕事、家事など様々な事情で時間が取れない方もいらしゃるかと思いますが、
それでもやる気と根気が続く限り限界はなく、
取り組み続けていればいつかは合格できる試験だと思っているので気長に頑張って参りましょう!!


