こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
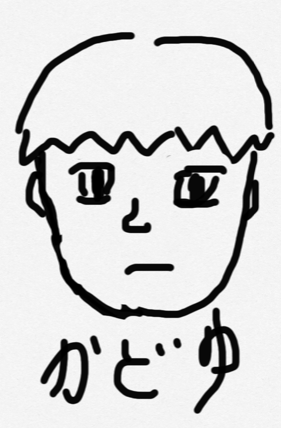
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は労働基準法解説の第7回目は第9条労働者の定義についてです。
前回と同様に定義の話になりますが、今後学習していく中で大事な「イメージすること」の補強になるかと思いますので今回も何卒よろしくお願いします!
労働者の定義
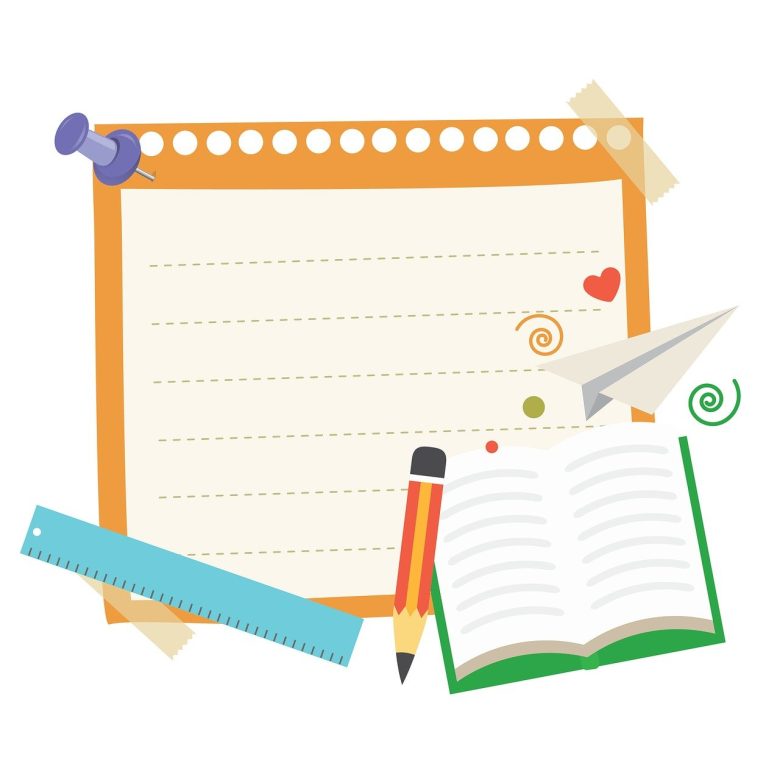
条文です!
第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
読み解いていきましょう!
ポイント
「使用される」というのは、雇用契約を交わし会社の指揮命令を受けて指揮監督下にあるといったところです。
そして労働力を提供し、その対償として賃金を支払われている人が「労働者」になります。
この労働者と会社の関係について「使用従属関係」といった言い方もします。
なので、正社員はもちろん、契約社員やアルバイト、日雇い労働者、派遣社員も含めて労働者となりますが、
上記の中では派遣社員については関係性を改めて確認した上で理解しておいた方がいいので次の記事で解説します!
他に労働者に該当するもの・しないものの例を下記に挙げておきます。
<労働者に該当する>
- 法人の役員で工場長や部長の職にはあるが業務執行権や代表権を持たず賃金を受ける者
- 会社に在籍したまま労働を免除され組合事務の専従が認められた労働組合の専従職員
- 大学病院の研修医
- 新聞配達員
まず①について、基本的に法人の役員というのは労働者となりません。
それでは①も法人の役員だから労働者には該当しないのでは?と思うかもしれません。
ですが、代表権等がなく工場長等を兼務して、
業務執行権を有する取締役等の指揮監督下で労働に従事しており、
労働の対償として賃金を受けているといったような人は労働者に該当します。
なので、株式会社の取締役だからといって労働者にならないと即判断するのは早合点かもしれません!
次に②について、
会社に在籍してるけど労働を免除されて組合に専従しているってそれはなに…?
となりそうですが、
上記の場合は従業員は一般的には休職扱いとなり会社との雇用契約関係は存続しているものとされ労働者に該当します。
そして③については、過去の判例が関連しています。
研修医が医療の資質向上を目的としたプログラムに参加し医療行為に従事したが、
病院側はそれは教育的な側面を持つもので上記のような状況においては研修医は労働者にあたらないといった主張をしたことがありました。
しかし最高裁は、研修においては病院の医療業務の一部を担っており、研修医は病院の指揮命令関係下にあったとして研修医を労働者とみなしたといったところです。
④の新聞配達はアルバイト等の請負契約で行われる場合ですが、
請負契約というのは一般的に使用されているとは言えず労基法は適用外とされます。
しかし実態として、
配達ルートや時間等が管理されており、会社の指揮監督下に置かれているといったようなケースでは労働者に該当すると言えます。
役職や肩書き、契約形態等それだけで判断するのではなく、「使用されている(雇用契約を結んでいる)」や「賃金が支払われている」等、複合的な要素であったり実態で見ていくことが大事ということが分かりますね!
次に労働者に該当しない例です!
<労働者に該当しない>
- 個人事業主
- 法人や組合等の代表者、執行機関たる者
- 生命保険の外務員
- 同居の親族
①は事業に使用されているわけでもなく労働の対償として賃金が支払われているわけではないので、
労働者に該当しないというのは分かりやすいですね!
次に②ですが、法人の役員というのは前述の労働者に該当する場合のところにも出てきましたが、
こちらは労働者には該当しません。
前述のものと何が違うかというと、記載の違いの通りではありますが、
こちらは代表権等の権限を有し、賃金が払われておらず役員報酬があるといったイメージです。
役員報酬というのは労働の対償ではないですし、
役員は雇用契約ではなく委任契約で就任するので②の例だと労働者性はないと言えるかと思います。
③はまずどのような人なのかというと、家庭や企業等を訪問して保険商品を契約してもらい顧客対応を行うようなイメージです。
顧客の都合に合わせて勤務時間が変わり、夜や土日などにも仕事をすることもあるようです。
そしてまたまた単に外務員という肩書きだからといって労働者じゃないと即断するのは危険でして…
以下の要素があれば外務員は労働者に該当しないとしています。
・生保会社との契約形態は業務委託契約とする
・成果報酬とする
・会社の職員と外務員で呼称の違いを分かりやすくする
・会社が労働の時間と場所について管理しない
なので、例えば外務員という肩書きながら成果に対する報酬ではなく、
会社が労働時間等の管理をしており、労働の対償として賃金を受け取っている等の場合は実質的に労働者ということになります。
最後に④同居の親族について原則は労働者となりませんが、
例のごとく以下の要素により労働者となることがあります。
・同居の親族以外の労働者を使用する事業で同様の業務に従事している
・上記のような業務に従事してそれに応じた賃金が支払われている
・明確に事業主の指揮命令に従っている
上記のような同居の親族は、
「事業に使用されてその労働の対償として賃金が支払われている労働者」
と同様な業務に指揮命令下で従事してそれに応じた賃金が支払われているので労働者になるといったところでしょうか。
同居の親族については、前回の労基法の適用事業の記事でも触れていますので併せてご確認いただけますと幸いです!
(よろしければ…↓)
それでは復習の条文です。
第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
ここらでまとめにいきたいと思います!
まとめ
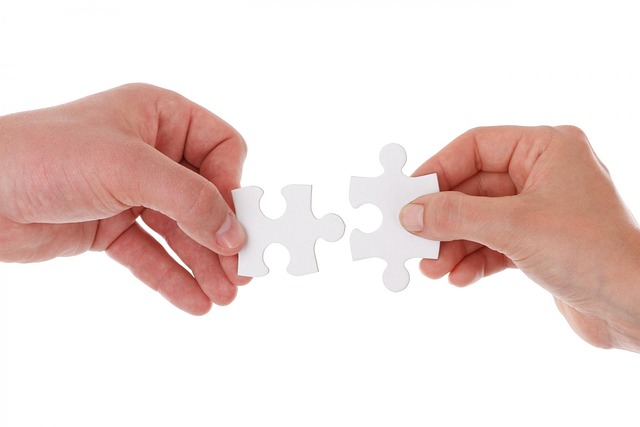
第9条労働者の定義
- 労働者は事業に使用(雇用契約を交わし指揮命令を受けている)されて、その労働の対償(業務委託契約において成果報酬とは違う)として賃金が支払われているか
- 労働者に該当する・該当しない具体例を呼称や肩書きだけではなく実態を見て慎重に判断する
繰り返しになってしまいますが、労働者か曖昧なものについては実態を見て労働者性を判断することが重要です。
(複合的に多角的に考えを巡らせることで見えてくるものがあるかもしれません)
パキッとした話ではなかったかもしれませんが、今回も重要なところなので何とか掴んでいきたいところです。
今回もお疲れ様でした!
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。
次回は第10条使用者の定義について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!



