こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
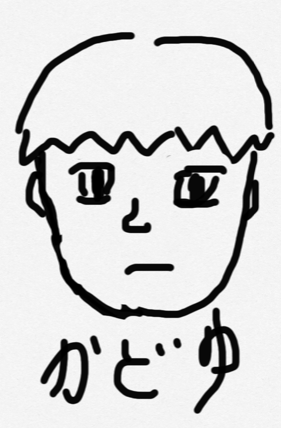
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は労働基準法解説の第6回目で労働基準法の適用事業についてです。
本来は第8条に位置するものですが改正により削除され、該当部分は労働基準法の中で移動しました。
言葉の定義や考え方が重要です!今回もよろしくお願いします!
「事業」とは

まずは条文から!ではなく…
上述の通り第8条は削除されているのでいきなり定義等の解説をしていきます。
「事業」は一般的に「会社」ということではなく、
工場や事務所、店舗等のように一定の場所で継続的に行われている作業の一体で、
必ずしも本店や工場等を総合して会社全体のことを指しているわけではありません。
なので、例えばX社に本店(東京)や支店(神奈川)、工場(埼玉)がある場合は、
それらは別々の事業として取り扱われます。
本店と支店はどちらもX社ですが、労働基準監督署の管轄はそれぞれの場所で行われます!
一つの事業であるかどうかは、
主として「場所的観念」によって決定すべきなんてことも厚労省の資料で言われています。
しかし…
別々の場所にあっても出張所や支所等で、
規模が著しく小さかったり事務能力も単独では成し得ない等で独立性がないものについては、
直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこととされています。
この例としては現場に事務所がない建設現場や、新聞社の通信部(地方のニュースを扱ったり支局や通信局を統括する部署)があります。
それでは、もし工場の中に診療所や食堂がある場合はどうなるでしょうか?
これについては労働の態様が著しく異なるとして、それらを切り離して独立した一つの事業とすることがあります。
他の例では新聞社の本社にある印刷部門も独立の事業とします!
「事業」の定義が分かったところで、適用される事業についていってみましょう!
適用事業について

労働基準法はほとんどすべての事業に適用されます!
原則、業として継続的に行われており、
労働者を使用している事業であれば労基法が適用されることになっています。
そして主要な事業については下記のように労働基準法別表第1に定められています。

(e-Gov法令検索の一部をスクリーンショットしたものです)
1号から5号までは工業的業種、6号から15号までは非工業的業種とも呼ばれており、
労働時間等の規定について一部の業種で取り扱いが異なっているので便宜上分けられています。
正直、この表の内容については個人的に必死で覚えた記憶がないのでこんなものがあるんだぐらいでいいかと思います。
重要なのは、この表に載っている事業にのみ労基法が適用されるものではないということです!
この表で便宜上分けているだけで全ての事業を網羅しているということではないということです。
原則があれば例外があるように次は適用が除外される場合について見ていきましょう!
適用除外のケース
いきなりですが…
日本の会社の海外支店について労基法の適用はどうなるでしょうか?
これは適用が除外となります。
属地主義といって日本の法令は日本国内にある事業のみに適用され、
事業としての実態を国外に備えているものには労基法は適用されません。
したがって日本にある外国の会社や、そこで働く外国の方には労基法が適用されるということです!
そしてまた別の大事なポイントですが、労基法第116条には、
「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」
とあります。
「同居の親族」というのは、居住や生計を同じくしている6親等内の血族(はとこも入る)、配偶者及び3親等内の姻族(義理の曾祖父母も入る)のことです。
なので同居の親族以外の労働者を使用すると労基法が適用となります。
次に「家事使用人」は、家政婦(夫)など家事一般に使用される者をいいます。
しかし家政婦紹介会社などに雇われている場合に、
出先である家庭の指揮命令の下で家事に従事しているなら「家事使用人」となりますが、
会社の指揮命令の下に家事を行うものは「家事使用人」ではなく「労働者」にあたりますので労基法の適用となります。
他に適用除外になるケースとしては一般職の国家公務員です。
これは国家公務員法にその適用除外となる根拠があります。
と言っても例外があります…
独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員については、国家公務員となりますが労基法の適用となります。
他には一般職の国家公務員ですが国有林分野に従事する現業職員も適用となることも頭の片隅に入れておきましょう。
因みに…行政執行法人とは独立行政法人の中の1種類だそうです。
なのでそれ以外の独立行政法人の職員さんは公務員ではないので当然に適用となります。
そして、外交官(日本に勤務して本国との連携を行う外国人)等の外交特権を有する者も適用除外になりますが、
上述したように外国の方が経営する事業や外国人労働者については当然のように適用となります。
一部適用除外のケース
部分的に労基法の適用が除外されることもあります。
それが一般職の地方公務員や船員の場合で、
この除外された部分については地方公務員法や船員法で補完されるという形になります。
しかし、公務員の一般職のうち現業職(清掃職員や学校給食員等)については、
職務内容が民間の同種の事業との類似性を鑑みて労基法のほとんどが適用となることも覚えておきましょう。
(ややこしくなるので読み飛ばしていただいても問題ありません…そして詳しい方、間違いのご指摘をいただけると助かります…)
僕も気になったので調べてみましたが、一般職の他に特別職というものがあるそうです。
特別職は明文化されており例としては、
国家公務員なら総理大臣、国会議員、その公設秘書だったりも…
地方公務員なら知事とか議員とか…
そして特別職は国家公務員法や地方公務員法が適用されないけども、
それぞれ特別職に法令が備わっているとのことです。(国会職員法など)
でもその特別職には国家公務員法や地方公務員法が適用されないからこそ、
労基法上の「労働者」なら労基法が適用されるとのこと…
まとめにいきます!
まとめ
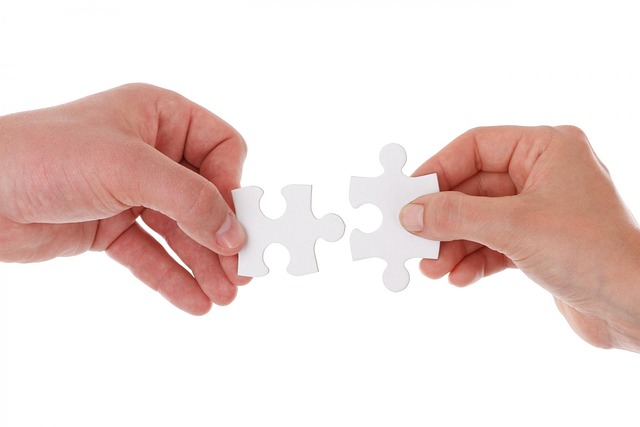
労働基準法の適用について
- 労基法において「事業」というのは「会社」全体ということではなく一つの場所で見る(本店と支店は別々の事業)
- 一つの場所に独立性がある部門が入っている場合は別々の事業になる(工場の中に診療所など)
- 別の場所にある事業でも規模が小さい等で独立性がないものは直近上位の事業と一括して一つの事業としてみる(現場事務所のない建設現場など)
- 法別表第1にある事業にのみ適用されるのではない
- 適用除外のケースを例外含めて覚えておく(同居の親族のみを使用する事業、家事使用人、公務員)
ちょっと多かったですね…
重要な部分なので頑張って覚えておきましょう!
因みに公務員は労基法以外にも労働組合法なども適用除外になることがありますが、
これは公益性の高いお仕事で市民生活に支障がなるべく出ないようにするためだそうです。
今回もお疲れ様でした!
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。
次回は第9条労働者の定義、第10条使用者の定義について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!


