こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>
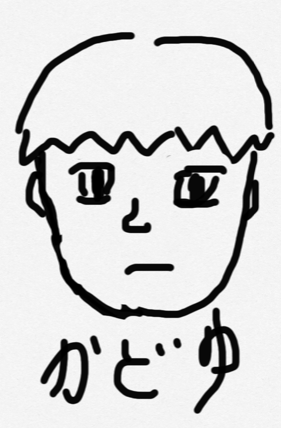
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は労働基準法解説の第3回目で第4条男女同一賃金の原則になります。
男女雇用機会均等法が関連するのでそれについても少し触れますが、
上記は社労士試験の科目の一つである「労務管理その他の労働に関する一般常識」の範囲なのでそちらで詳しく触れていきたいと思います。
それでは今回もよろしくお願いします!
男女同一賃金の原則

今回も条文から!
第四条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
内容を解説する前にちょっと背景を…
第4条は、第3条には規定がなかった「女性」であることを理由に「賃金」について差別的取扱いを禁止しています。
第3条について解説した記事はこちら↓
なぜ第3条には性別についての規定がなかったかというと、
労働基準法の制定時には女性保護の必要性を重視して労働条件における性差別を禁止しなかったからだそうです。
昔は、一般的に男性と比べて女性には過酷な労働条件を課すのは難しいので、そこには差があっても仕方がないと考えられていたといったところでしょうか。
しかし賃金に限り本条において規定されております。
これは歴史的に男性労働者よりも低位にあった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を図り、
男性との賃金の差があってはならないといった趣旨で定められています。
ポイント
それでは内容について触れていきたいと思います!
本条で禁止されている「女性であることを理由として」という中には、
労働者が女性だからということはもちろん、
「女性労働者が一般的又は平均的に勤続年数が短い、能率が悪い、主たる生計維持者ではない」といった認識や印象により不当な扱いを受けることも含まれます。
女性だからというだけでなく「女性は〇〇だから…」というのも禁止されているということです!
例えば、平均的に女性は勤続年数が少ないというデータがあるから、一般的に女性は家計を支えている第一人者ではないからといったことです。
「一般的又は平均的」にそうだからといって、個人で見た時に差をつけられてはたまったもんじゃありませんよね…
なので男女間で実際に、職務、能率、技能、年齢、勤続年数等に応じて違いがある場合には、
それに応じて賃金に差異が生じることは本条の違反とはなりません。
そして賃金というのは、賃金額そのものだけでなく給与形態等を含むので、
例えば男性は月給、女性は時給とするようなことは本条違反となります。
それでは、賃金以外についての労働条件(昇進や定年等)に差をつけることは許されているのでしょうか?
これらは本条ではなく「男女雇用機会均等法」で禁止されていることとなりますので、
後に少しだけ触れます!
そして罰則ですが労働基準法第4条に違反した場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
が科されることがあります。
それでは復習の条文です!
第四条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
次に男女雇用機会均等法について少しだけ…
男女雇用機会均等法
最初に書いたように、社労士試験において労働基準法の範囲ではありませんが関連しているので触れておきます。
男女雇用機会均等法は募集・採用や配置、昇進、福利厚生、職種・定年・解雇・労働契約の更新など、
労基法第4条に規定がない賃金以外の様々な面において性別による差別を禁止しています。
また、婚姻や妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いや、セクシャルハラスメントの禁止についてもこちらに規定があります。
労働基準法第4条を補完したような法律といったところですね!
まとめにいきましょう!
まとめ
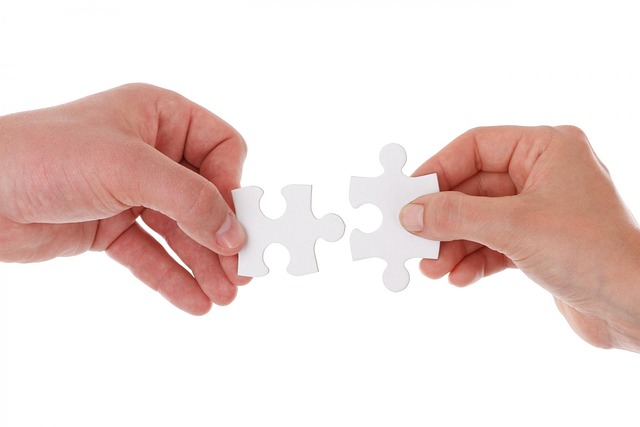
第4条男女同一賃金の原則
- 単に「女性」であることを理由とする以外に「女性は一般的に勤続年数が短いから」といったことで不当に賃金について差をつけることも禁止されている
- 実際の職能や勤続年数等で、男女で賃金の差が生じることは本条違反ではない
- 差別的取扱いをしてはならない「賃金」には賃金額だけでなく給与形態(月給や時給)等も含む
今回は第4条男女同一賃金の原則について書いていきました!
なお第3条と同じように、
男性に比べて女性を不利に扱うだけでなく有利に扱う場合も本条の違反
となりますので注意しておきましょう!
今回もお疲れ様でした。
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。
次回は労働基準法第5条強制労働の禁止、第6条中間搾取の排除について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!



